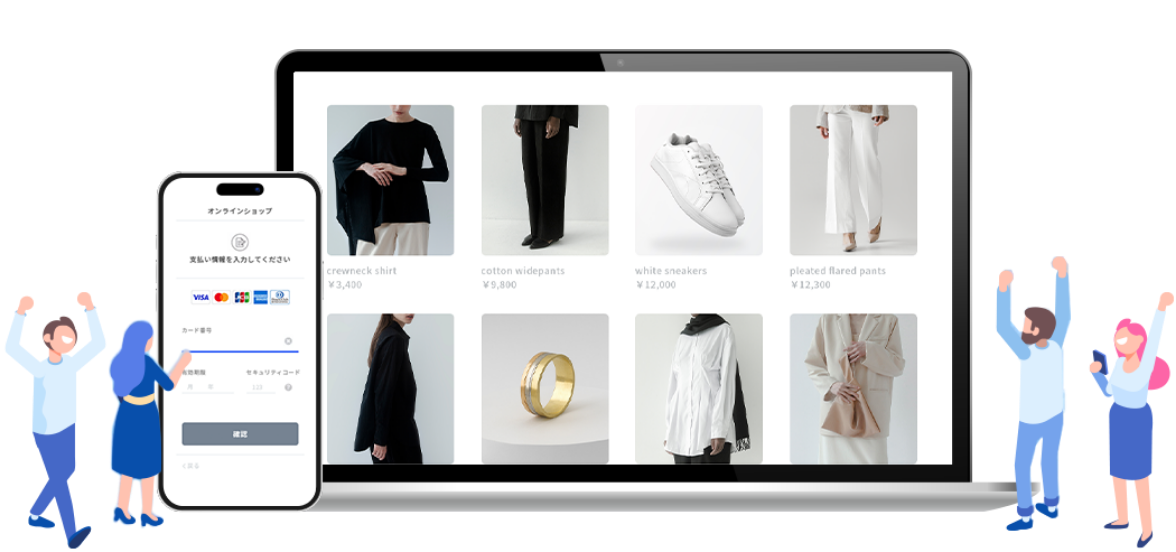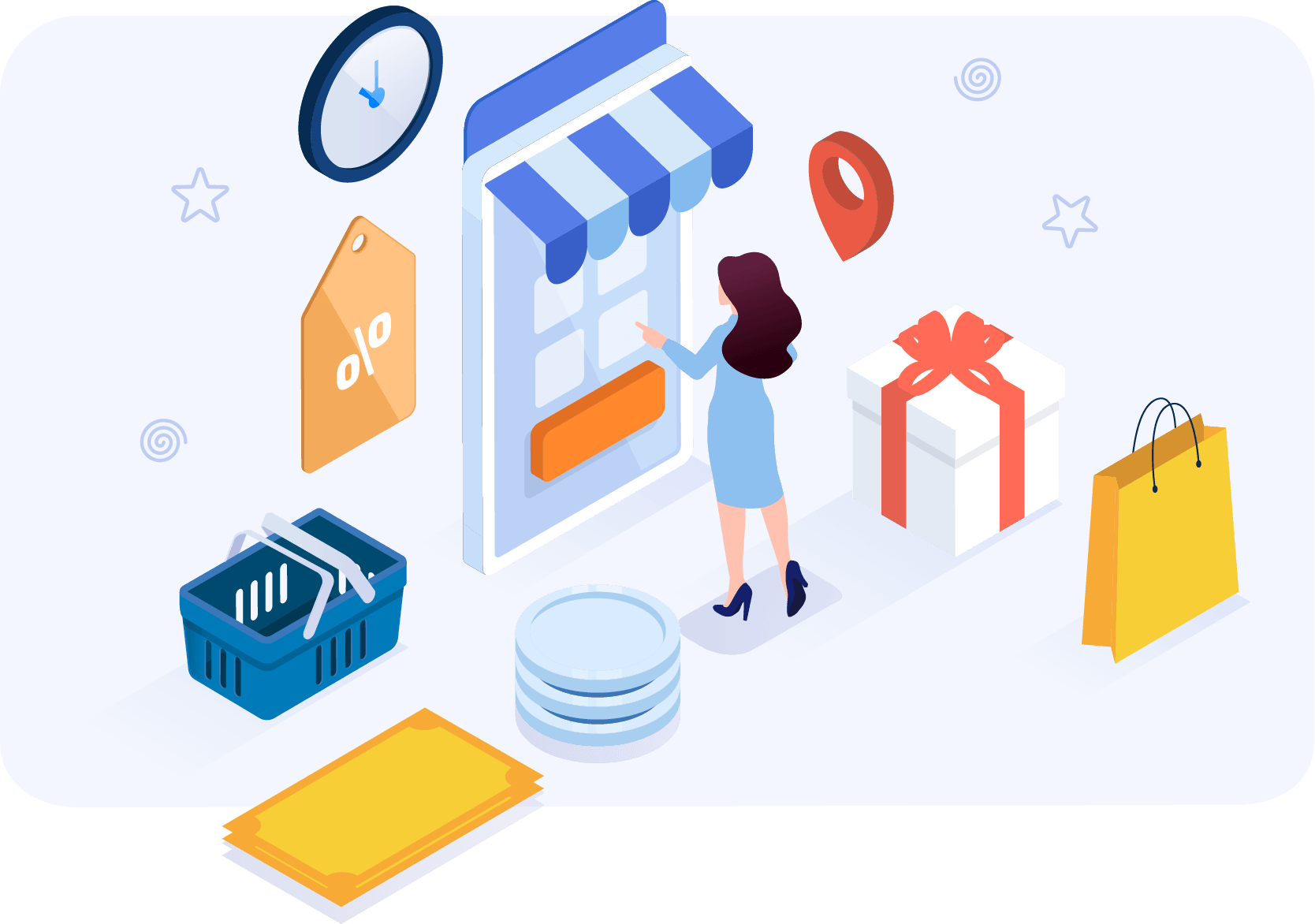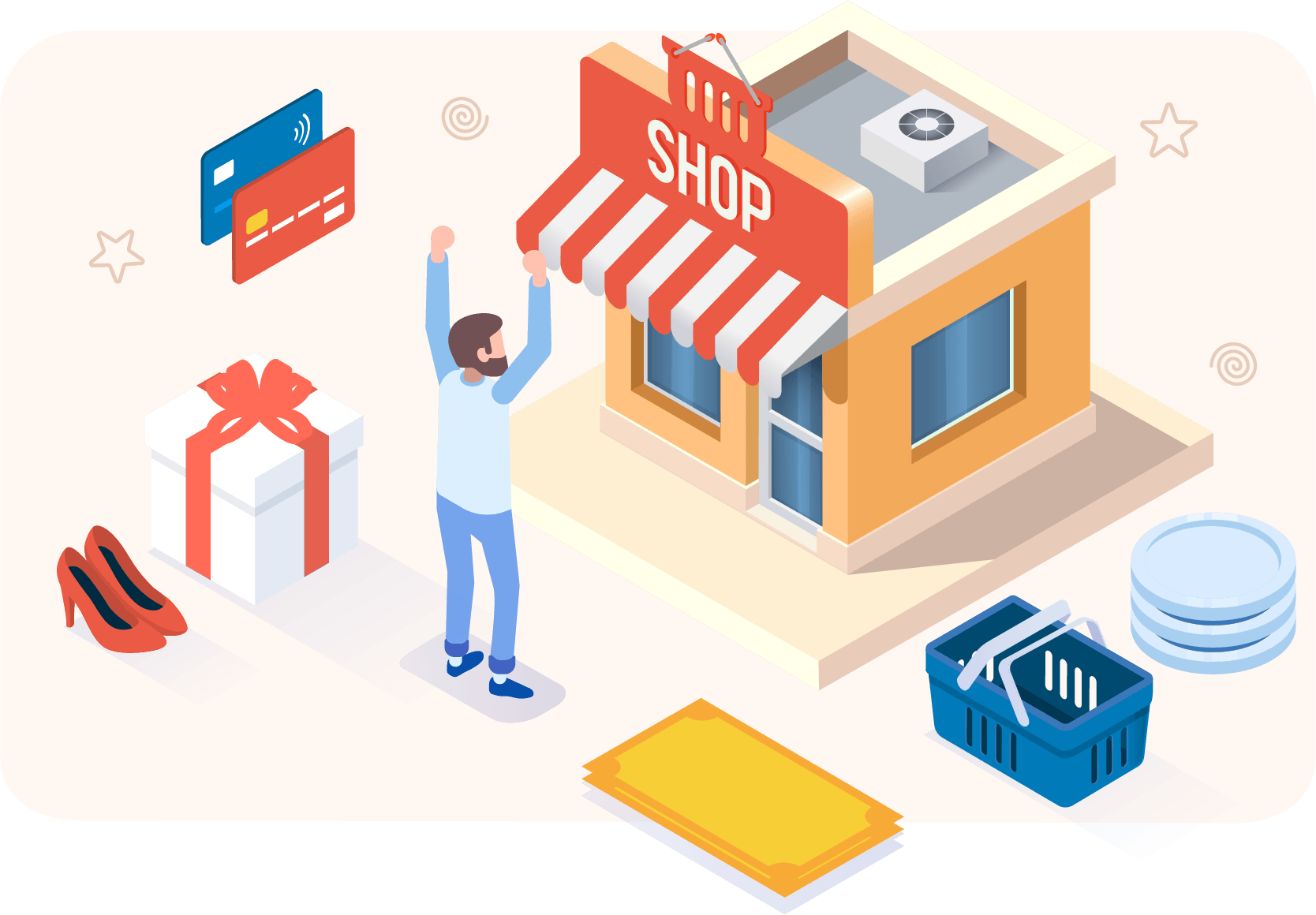Pay-easy(ペイジー)は、ATMや銀行ネット決済を通じて、税金や各種料金の支払いができる便利な決済方法です。そもそも、Pay-easyの決済はどのような仕組みになっており、お客さまや事業者さまにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
本記事では、Pay-easyの仕組みや利用・導入のメリットのほか、Pay-easyの導入が向いている業種と、Pay-easyを導入する流れについて解説します。Pay-easyの導入を検討する際の参考にしてください。
オンライン向け決済
「決済手段が限られている」「利用されやすい決済がわからない」そんな悩みはありませんか?
SBペイメントサービスでは、オンライン決済サービスの機能紹介に加え、ユーザーがよく利用する決済手段に関する調査結果をまとめた資料をご用意しました。
目次
Pay-easyはATMや銀行ネット決済で支払いをする決済方法
Pay-easyは、ATMや銀行ネット決済を通じて税金、各種料金を支払うことができる決済方法です。日本マルチペイメントネットワーク推進協議会(JAMPA)が提供しており、金融機関、収納機関(税金や各種料金の納付先)、そしてお客さまをつなぐ「マルチペイメントネットワーク」というインフラを活用しています。
Pay-easyは、全国の多くの金融機関に対応しており、お客さまが普段利用している銀行口座から直接支払いができる点が大きなメリットです。加えて、税金や公共料金、通信費、通販代金などの支払いにも幅広く対応しており、日常生活やビジネスのさまざまな決済シーンで活用されています。
Pay-easyの2024年度の取扱件数は約1億5,000万件、取扱額は約79兆円に達しており、いずれも前年から2桁成長を記録しています。サービス開始以来、23年連続で増加しており、今後もさらなる普及が見込まれる決済方法といえるでしょう。
出典:日本マルチペイメントネットワーク推進協議会「電子決済「ペイジー」 取扱件数 1.5 億件に」(2025年4月)
Pay-easyを使ったお支払いの流れ
お客さまがPay-easyを通じてお支払いをする流れは、大きく2通りあります。ここでは、それぞれのお支払いの流れを紹介します。
請求書などからのお支払い
Pay-easyは、請求書などに記載されたPay-easyのお支払い用の番号を使うと、税金や各種料金のお支払いができます。請求書などからのお支払いの流れについて見ていきましょう。
1. Pay-easyのお支払いに使う番号を確認する
最初に、請求書や納付書、ECサイトからの請求メールなどに記載されたPay-easyのお支払いに使う番号を確認します。
Pay-easyのお支払いに使う番号は、以下のとおりです。
請求書などに記載されたPay-easyのお支払いに使う主な番号
- ・国・地方公共団体の場合:収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分
- ・一般企業の場合:収納機関番号、お客さま番号、確認番号
2. 金融機関のATMもしくは銀行ネット決済にアクセス
Pay-easyのお支払いに使う番号を確認したら、金融機関のATMもしくは銀行ネット決済にアクセスします。
ATMを利用する場合は、Pay-easyのお支払いに対応しているATMに行く必要があります。Pay-easy対応のATMは、Pay-easyのWebサイトで確認可能です。なお、Pay-easyはコンビニの共用ATMではお支払いができないため、注意しましょう。銀行ネット決済でお支払いをする場合は、利用する金融機関のインターネット決済ページにアクセスしてください。
3. 番号を入力して支払う
最後に、請求書などに記載された番号を入力してお支払いをします。
金融機関のATMを利用する場合は、ATMのメニューでPay-easyを選択し、請求書などに記載された番号を入力しましょう。銀行ネット決済を利用する場合も、お支払いのメニューでPay-easyを選択し、請求書などに記載された番号を入力してお支払いをしてください。
ECサイトからのお支払い
Pay-easyは、対応しているECサイトなら、直接支払うこともできます。ECサイトからのお支払いの流れは、以下のとおりです。
1. お支払い方法でPay-easyを選ぶ
Pay-easyに対応しているECサイトで商品・サービスを購入する際、お支払い画面でPay-easyでのお支払いを選択します。
2. 銀行ネット決済が可能な金融機関を選ぶ
ECサイトでPay-easyでの支払いを選択すると、銀行ネット決済に対応している金融機関を選ぶ画面に遷移します。引き落としをしたい金融機関を選びましょう。
3. お支払い情報を確認して支払う
金融機関を選んだら、銀行ネット決済にログインします。その後、お支払い情報を確認できる画面が表示されますので確認してください。お支払いボタンを押したら、お支払い完了です。
Pay-easy決済の仕組み
お客さまがPay-easyを利用してお支払いを行うと、金融機関、税金や公共料金の支払いを受け付ける収納機関(国・自治体・企業)などを経由して決済が行われます。
SBペイメントサービスが決済代行を行う場合は、SBペイメントサービスが加盟店さまと収納機関のあいだに入り、決済処理を代行いたします。加盟店さまは、決済処理や入金といった手間をかけることなく決済処理を進められます。
SBペイメントサービスが決済代行を行う場合の、Pay-easy決済の仕組みは以下のとおりです。
SBペイメントサービスによるPay-easy決済の仕組み

お客さまがPay-easyを利用するメリット
お客さまには、Pay-easyを利用するいくつかのメリットがあります。主なメリットは以下のとおりです。
24時間365日、いつでもお支払いができる
Pay-easyを利用すれば、24時間365日いつでもお支払いができます。
Pay-easyでは、自治体の窓口だけでなく金融機関のATM、銀行ネット決済などでもお支払いが可能です。窓口の受付時間内にお支払いができない場合でも、ATMを利用すればお支払いができるほか、銀行ネット決済なら休日や祝日、どの時間帯でもお支払いができます。
クレジットカード情報を渡すことなくお支払いができる
Pay-easyを利用すると、事業者さまや収納機関にクレジットカード情報を渡すことなくお支払いができます。クレジットカードを持っていないお客さまにとっては、大きなメリットといえるでしょう。
また、ATMや銀行ネット決済を利用すれば、Pay-easyのお支払いに必要な請求書、納付書を窓口の担当者などに提示する必要がありません。プライバシーが守られたままお支払いを完了できます。
お客さまがPay-easyを利用するデメリット
お客さまにとって、Pay-easyを利用することには複数のメリットがありますが、注意したいデメリットもいくつかあります。ここでは、お客さまがPay-easyを利用する際に知っておきたいデメリットについて見ていきましょう。
銀行ネット決済を契約していないと利用できない
Pay-easyをATMではなく銀行ネット決済で利用したい場合、お客さまは事前に金融機関で銀行ネット決済を契約しなくてはなりません。
ATMでのお支払いであれば、銀行ネット決済の契約は不要ですが、24時間365日いつでもお支払いができるメリットが得られなくなります。銀行ネット決済でPay-easyを利用したい場合は、事前に契約を済ませておくことが必要です。
ポイント還元がない
Pay-easyを通じたお支払いには、クレジットカードやPayPayのようなポイント還元はありません。
クレジットカードのポイント還元は、お買い物や特典交換にも使えるお得なサービスです。しかし、Pay-easyにはそうしたサービスがないため、お客さまによってはデメリットに感じられるでしょう。
事業者さまがPay-easyを導入するメリット
Pay-easyの利用は、お客さまだけでなく事業者さまにとっても複数のメリットがあります。ここでは、事業者さまがPay-easyを導入するメリットについて見ていきましょう。
新たな顧客層を開拓できる
事業者さまは、Pay-easyを導入すると現金払いや銀行振込に慣れているお客さまにも対応でき、新たな顧客層を開拓できます。
前述のとおり、Pay-easyはクレジットカードを持っていないお客さまも利用可能です。クレジットカード決済やバーコード決済は、すでにお客さまが利用していますが、Pay-easyを導入すれば、そうした決済方法を利用していないお客さまの決済ニーズに応えられるでしょう。
入金をリアルタイムに確認できる
入金をリアルタイムに確認できる点も、事業者さまがPay-easyを導入するメリットです。
Pay-easyを利用した決済では、事業者さまは決済情報を即時に入手できます。これにより、決済完了の確認のタイムラグが生じにくくなり、誤って再請求処理をすることもなくなるでしょう。
事務作業を軽減できる
事業者さまがPay-easyを導入すれば、事務作業の軽減も可能です。
Pay-easyを活用することで、振込明細の照合や入金確認にかかる作業を削減できます。取引件数が多い企業にとって、事務作業の効率化はコスト削減にもつながるでしょう。
Pay-easyの導入に適した業種
Pay-easyは、通信業、出版業、保険会社、クレジットカード会社、ネット通販、学校法人など、幅広い業種で導入されています。
これらの業種では、お客さまに各種料金や手数料などの定期的な支払いが発生するケースが多く、Pay-easyでの決済が向いているといえます。
さらに、公共料金や税金の支払いを取り扱う地方自治体、金融関連業界も、Pay-easyの導入が向いている業種です。Pay-easyを導入することで、お客さまは自宅や外出先からでも簡単に支払いができるため、結果として顧客満足度や回収率の改善にもつながるでしょう。
Pay-easyを導入する際の流れ
Pay-easyを導入するには、サポートをしてくれる会社を見つけ、所定の手続きをとる必要があります。ここでは、Pay-easyを導入する際の流れについて解説しますので、導入を検討している事業者さまは参考にしてください。
1. 収納代行事業会社を選ぶ
Pay-easyを導入するには、最初にPay-easyの導入をサポートしてくれる、収納代行事業会社の選定が必要です。複数の事業会社を比較し、導入実績やサポート体制、セキュリティレベルなどを確認してください。
2. 収納代行サービスを申し込む
自社に合った収納代行事業会社を選んだら、Pay-easyの決済代行サービスの申込みと契約を行います。事業会社が提供する申込みフォームなどから手続きを行うと、事業会社側で審査が行われ、問題がなければ契約が完了します。
3. サービスを開始する
事業会社との契約が完了したら、事業会社が定める所定の手順に沿って、システム設定と接続テストを行います。
システム設定は、請求情報の受け渡しをするうえで重要です。テスト用のデータなどを用いてテストを行い、お客さまが問題なくお支払いできることを確認したら、サービスを開始しましょう。
Pay-easyを導入するなら決済代行会社の利用がおすすめ
Pay-easyを導入すると、事業者さまは新たな顧客層を開拓しやすくなるほか、入金のリアルタイムな確認や事務作業の軽減が可能になり、多くのメリットがあります。
Pay-easyを導入するには、Pay-easyの決済をサポートしてくれる収納代行会社に申込みを行う必要がありますが、決済代行会社を経由して導入することも可能です。
決済代行会社のSBペイメントサービスでは、事業者さまの課題や要望に応じて、Pay-easy決済をサポートいたします。Pay-easyを導入される際には、SBペイメントサービスをぜひご検討ください。
よくあるご質問
- Q.
- Pay-easyとは?
- A.
- Pay-easyとは、ATMや銀行ネット決済を利用して税金や各種料金を支払うことができる決済方法のことです。2024年度の取扱件数は約1億5,000万件、取扱額は約79兆円に達しており、サービス開始以来、23年連続で増加しています。
- Q.
- Pay-easyの導入方法は?
- A.
- Pay-easyを導入するには、まずPay-easyの決済をサポートしてくれる収納代行事業会社を選び、サービスを申し込みます。システム設定や接続テストを行い、問題なければサービスを開始可能です。決済代行会社を活用すれば、申込みから運用開始までスムーズに進められるでしょう。
- Q.
- Pay-easyで支払う際に、会員登録は必要か?
- A.
- 必要ありません。決済時に払い出される「収納機関番号」「お客さま番号」「確認番号」のみでお支払いいただけます。
- Q.
- 支払期限を設定することはできる?
- A.
- はい、可能です。決済翌日~59日のあいだで必ず支払い期限を設定していただいております。
その他のご不明点はFAQ よくあるご質問をご確認ください。